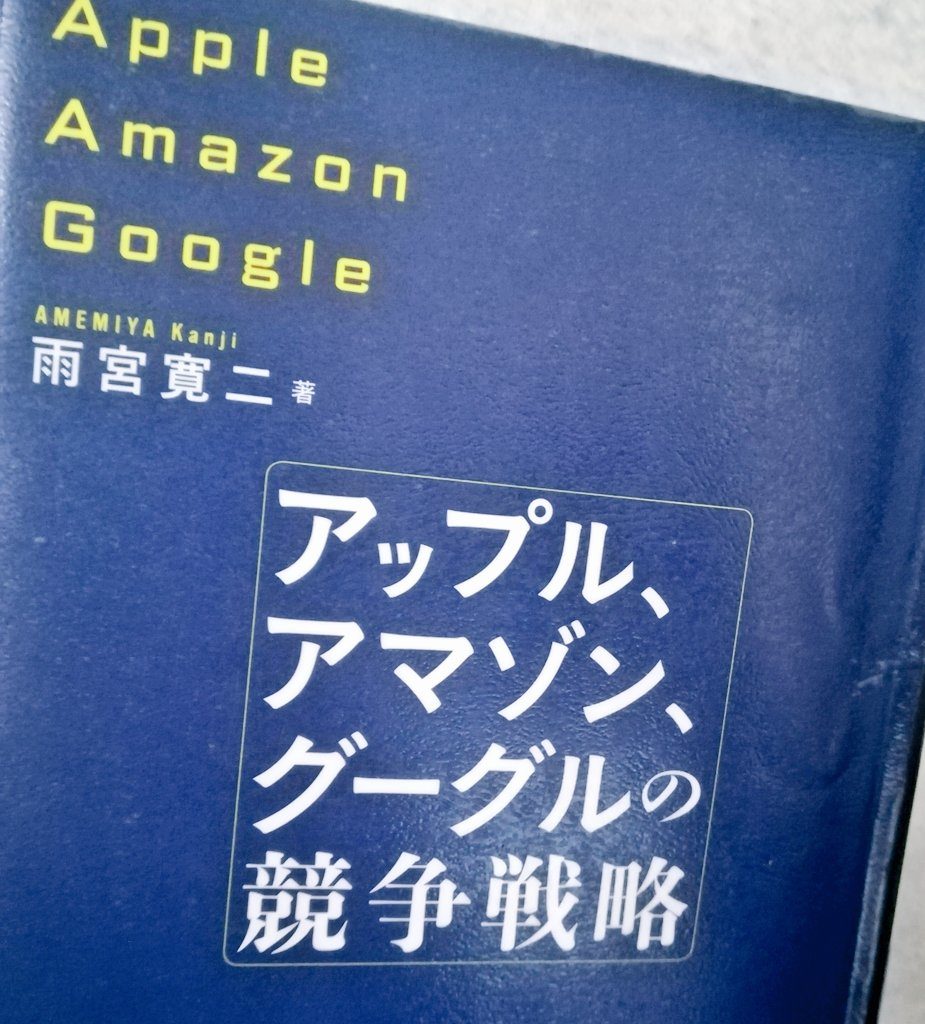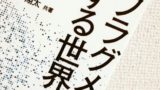『アップル、アマゾン、グーグルの競争戦略』とは?
『アップル、アマゾン、グーグルの競争戦略』とは、株式会社情報通信総合研究所シニアアナリストである雨宮寛二氏の執筆でNTT出版株式会社より出版されました。
どんな内容?あらすじは?
『アップル、アマゾン、グーグルの競争戦略』は、インターネットの発展とネットビジネスを考える上で、GAFAのうちGAAに主軸を置いて説明した本です。
第一章が、インターネットの発展とインターネット・ビジネス
第二章が、戦略と分析手法の考え方
第三章が、アップルの戦略とイノベーション
第四章が、アマゾンの戦略とイノベーション
第五章が、グーグルの戦略とイノベーション
第六章が、プラットフォームの競合と戦略分析
合計6章で構成されています。
『フラグメント化する世界 ーGAFAの先へー』や『5Gビジネス』、『the four GAFA 四騎士が創り変えた世界』に似た内容となっています。
ネタバレ
『アップル、アマゾン、グーグルの競争戦略』では、Google、Amazon、Appleの3社の企業戦略と、ビジネス成長に注目して、それぞれ解説されています。
例えば、Amazonでは、もともとオンライン書店としてスタートし、現在では書籍に留まらず、豊富な品数を揃えるオンラインショップへと成長しています。
2005年には、Amazonピンゾンという独自のプライベートブランドを立ち上げたり、2006年には、ウェブサービ氏、AWSを提供し、サーバーやストレージ(記憶装置)などの膨大なクラウド・コンピューティングを提供。活用できるように範囲を広げました。
2007年には、電子書籍市場に参入しキンドルの発売を行うなど事業を展開させているのです。
Appleの場合
Appleは、1997年にネクスト買収として、一度離脱したジョブスが復帰。同年マイクロソフトと特許のクロスライセンスや技術開発契約を結びました。
その後、ジョブスはiMacプロジェクトとして2000ドル以下の低下価格帯のコンシューマ向けPCモデルの開発をスタートし、1998年にiMacを1299ドルで発表。日本を始め、北米、ヨーロッパ市場で27万8000台の販売を記録したのです。
2011年には、iTunes1.0(音楽再生管理ソフト)を発表し、初代iPodを発表。
2007年にiPhoneをハッpyっっっっっっっ様するなど、デバイスを中心に展開していきました。
経済範囲の考え方
鉄道会社が旅客用の車両を走らせる目的で電車の線路を建設した際に、この線路を貨物用の車両に用いることができれば、この会社の範囲の経済は、多角化を実現し、同一の経営資源を複数の事業や製品で共有し合うことにより、効率性を高めることができるのです。
鉄道会社が、線路建設コストに関わる輸送事業あたりの平均コストを抑えることができるため、単独で旅客輸送事業と貨物輸送事業をプライシングの自由度が高まる利益性の向上につながります。
Googleの場合
Googleの基本戦略は、無料の最大化戦略です。
自社のあらゆるサービスを無料にして、最大の市場にアプローチができます。
2010年に293億2100万ドルの売上高を達成。
Googleの検索サービスを主軸にし、基盤技術、ウェブアプリの3つに分けられています。
2010年にはアンドロイドOSを展開し、世界販売台数が6722万4500台うぃ達成、2009年には679万8400台と比較し、インターネットテレビを普及させ、Googleの検索エンジンとの連動を可能にし、広告収入を拡大をしました。
パレートの法則
企業が収益化を図る上で、考えるのは効率性です。人気商品や売れ筋商品を多数取り揃え、そうでない商品を店頭から外せば効率性が高まります。
クリス・アンダーソンの『ロングテール』の中で、「文化と経済が受容曲線のヘッドにある比較的少数のヒットに焦点を合わせるのをやめ、テールにある無数のニッチへ移行する」とし、パレートの法則と呼ばれています。
商品の上位20%が全体の売上80%を占めながら、売れない90%の商品が売上全体の25%を占め利益全体では33%を占めているのです。
つまり、売れない商品を集めれば、売れる商品に匹敵する市場が作られるわけです。
まとめ
GAFAのうち、フェイスブックを除いた3社に着眼をし、ビジネス戦略を説明した本書『アップル、アマゾン、グーグルの競争戦略』。
GAFAビジネスの各書を読む前に本書を読んでおくと、よりスムーズに理解できておすすめです。